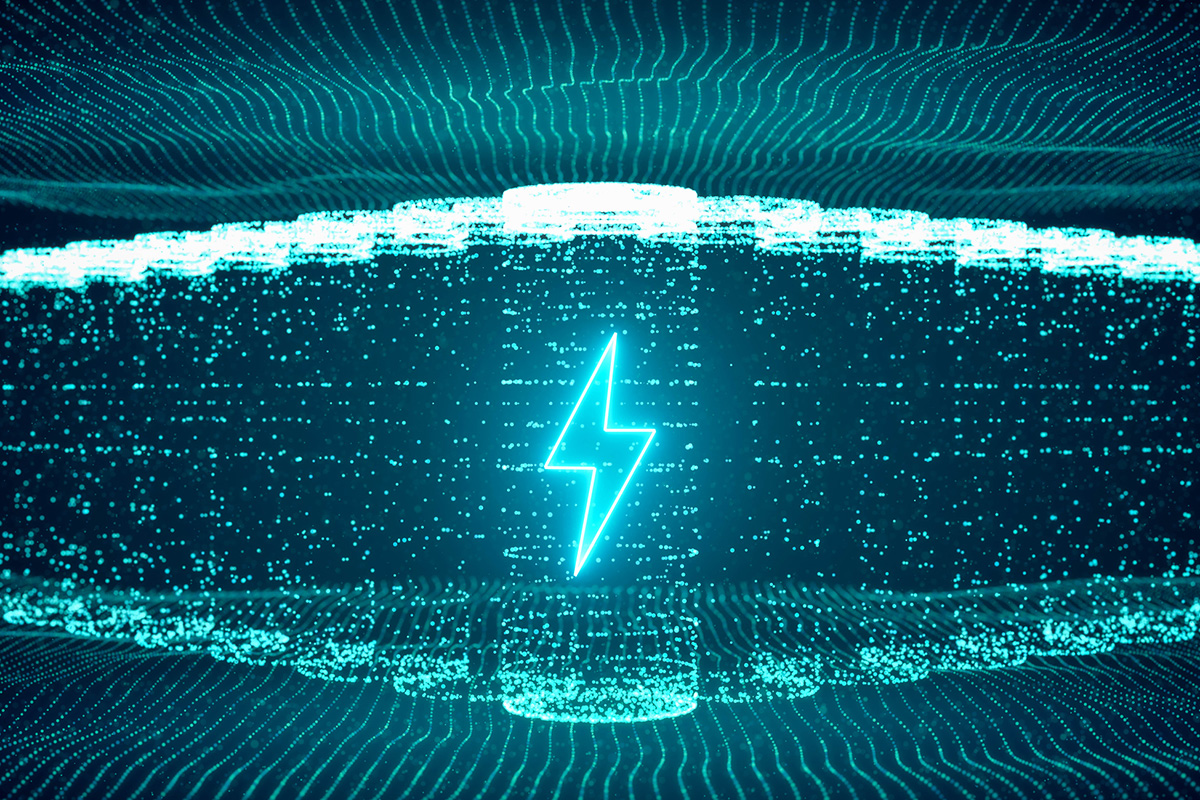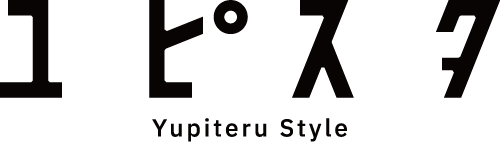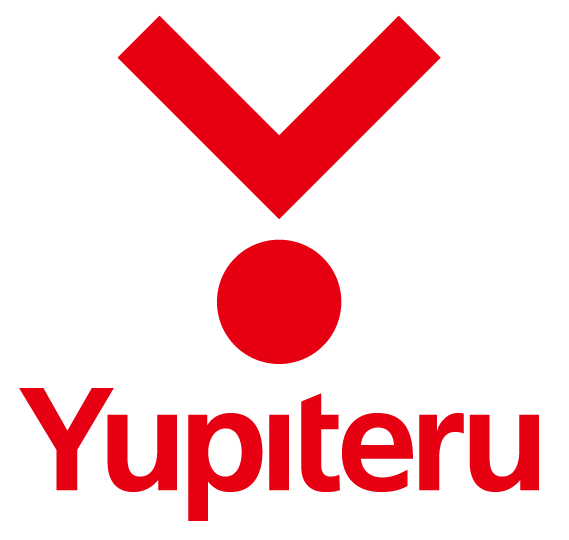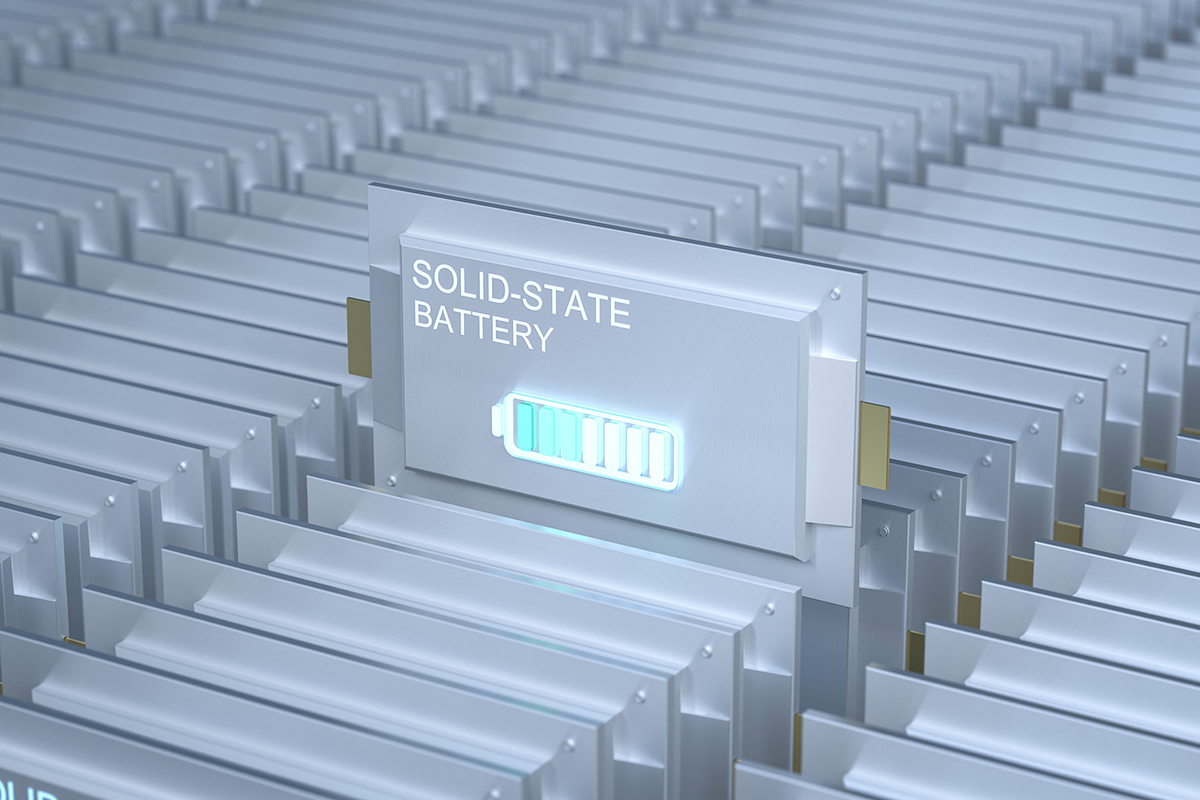現代の生活に欠かせないテクノロジーを支えるのが電気です。しかし一方で、電気代の高騰が続いており、家庭で「電気を貯めて使う」、バッテリーの上手な使い方にも関心が高まりつつあります。今回は、日常に溶け込んできた「家庭用蓄電池」と「電動アシスト付き自転車」に注目してみましょう。どちらも私たちの暮らしを便利で快適なものにするものとはいえ、導入時に軽くない負担がかかるのも事実。そこでこれらの製品を長く使うため、さらにサステナビリティの視点からも、バッテリーを長持ちさせるポイントについて解説します。
家庭用蓄電池とは、発電所から供給される電力や、太陽光発電で発電した電力を貯めておける大型のバッテリーです。特に太陽光発電と組み合わせ、太陽光発電で余った電力を充電するという使い方が近年注目されています。電気の自給自足率を上げて電気代を節約し、停電対策にもなりながら、さらにCO2排出量削減も期待できます。
ただネックはその設置費用です。使い方にもよりますが、家庭用蓄電池設置の相場は一般的な家族に適したサイズのもので100〜300万円ともいわれます。補助金や助成金の制度を利用できるケースもあるとはいえ、かなりの金額です。購入後はできるだけ長く大切に使って、しっかり元を取りたいものですよね。家庭用蓄電池にはいくつか種類がありますが、バッテリー寿命という面から考えるとリチウムイオン電池を使用している製品がおすすめです。
蓄電池はフル充電から充電がなくなるまでを1サイクルとした「サイクル回数」が決まっており、サイクル回数が増えるごとに劣化します。そこで重要なのは過充電・過放電を避けること。スマホのバッテリーは0%にならないようにすることと充電する際に100%を避けることが劣化を防ぐといわれているのですが、家庭用蓄電池でも同じです。0%まで使い切らず、残量を少し残しておいて再充電するなどの運用を心がけ、サイクル数を一日一回に抑えましょう。
また、高温多湿の場所や直射日光の当たる温度変化の大きな場所を避けて設置をし、充電がされるまでにいつもよりも時間がかかる、蓄電池が熱いなどの異常を感じたら早めにメーカーに相談しましょう。とはいえ、異常がなくても定期的なメンテナンスを行い、日頃から点検を心がけて長く使用したいものです。
近所のスーパーへの買い物や坂道、子どもの送り迎えなど、日常のさまざまな場面で頼もしい存在なのが電動アシスト付き自転車。チャイルドシート付きやシニア向けの三輪タイプなども登場し、年々普及が進んでいます。しかし一般的な自転車と比較すると価格は高めで、製品によっては20万円以上するものもあります。
電動アシスト自転車のバッテリーも家庭用蓄電池と同様にリチウムイオン電池が主流なので、バッテリーを長持ちさせるように使うには、やはり充電方法がカギとなります。
急速充電は、短時間で素早く充電できる便利な機能ですが、充電時に発熱しやすく、バッテリーの劣化を早める可能性があります。このため、普段の充電は、できるだけ急速充電を避けるのがポイントです。
また、サイクル回数(充電回数)を減らすために、できるだけ充電残量が減っているのを確認してから充電しましょう。ただし減らし過ぎはNG。0%になる前に充電し、80%程度で充電をストップさせます。電動自転車を使用しない日が多くても、月に一度はバッテリー残量のチェックを。自然放電でバッテリーが空にならないようにすることも長寿命化のコツです。
また、バッテリーは暑さや寒さ、直射日光を避けての保管がおすすめです。電動アシスト自転車を屋外に駐輪しているなら、夏や冬のあいだはバッテリーだけ取り外して室内で保管しておくと安心ですよ。
電動アシスト自転車は、乗り方もバッテリー寿命に影響するといわれています。
電動アシスト自転車での走行が一般の自転車に比べて楽なのは、ペダルを漕ぐ力をモーターでサポートし、加速してくれるからです。つまり電力を消費するのは走り出しや登り坂のように、ペダルを漕ぐ力が必要なときなので、「走り出しは軽いギアにする」「道路に合わせたアシストモードの切り替えを行う」など適切なギアやモードの選択をするとよいでしょう。
また、タイヤの空気を定期的に入れたり、必要な部分に油をさすなど、自転車が軽快に走れるように整備することも、バッテリーへの負担を減らし長く使うことに繋がります。
☆バッテリーの寿命についてはこちらでも解説しています。
・リチウムイオン電池の寿命 スマホや電気自動車のバッテリー劣化を防ぐ
家庭用蓄電池や電動アシスト自転車にも使われているリチウムイオン電池は、今の私たちの暮らしに欠かせない存在です。一方で、いつかは寿命を迎えるリチウムイオン電池の廃棄問題もクローズアップされています。
同じくリチウムイオン電池で動くEV車のバッテリーは、2019年は約50万tだった廃棄量が、2040年には2,000万tを超えると予想されています。しかもリチウムイオン電池は有害物質を含むので、安全に廃棄するためには適切な処理が必要不可欠です。
しかしながら、近年、市区町村で回収する不燃ごみなどに混入したリチウムイオン電池に起因する発火事故が問題となっています。これを受け、リチウムイオン電池の回収を実施する自治体が増加しているものの、回収されたうちの半分程度は埋立・焼却・ストックされて再資源化されないままとなっています。
リサイクル率が上がれば環境リスクを減らし、電池に含まれている貴重な希少金属の回収も可能になるでしょう。
一方で、少しでもバッテリーを長く使う「バッテリー長寿命化」のための研究も行われています。
スマホの場合、AIを活用して充放電を制御したり、ユーザーの充電習慣を覚えて最適化させるなどの技術が開発されています。
こうした方法は今後、他の電気製品にも活用されていくでしょう。
家庭用蓄電池からモビリティまで、環境負荷低減と長寿命化を両立するバッテリーの取り組みは進み、さらに、安全で長寿命である「固体電池」への進化も見えつつあります。
私たちも、日ごろ使っているリチウムイオン電池の特性を理解してバッテリーを上手に使用し、また使用済み電池があれば放置せずにリサイクルに回すなどの方法で、環境保護や資源確保に協力したいものです。
☆電池についてはこちらでも解説していますのでぜひご覧ください。
・全固体電池とリチウムイオン電池はどう違う?自動車の未来は?
家庭用蓄電池にしろ、電動アシスト自転車にしろ、バッテリー寿命を長持ちさせる基本は「温度管理」と「適切な充電」です。リチウムイオン電池の仕組みと対策を理解し、長期的に安心して使えるエネルギーライフを実現しましょう。